30代で歯を失うという現実に直面したとき、多くの人々はどのようにその状況を乗り越えるのでしょうか。義歯、ブリッジ、インプラントといった欠損補綴治療にはそれぞれ特有のメリットとデメリットが存在しますが、果たしてどの治療法が最も適しているのでしょうか。
本記事では、30代における喪失歯数の現状から始まり、各補綴治療の割合や特徴について詳しく掘り下げます。特に、若い世代の入れ歯使用割合や治療費についても触れ、入れ歯の可能性とその制約を探ります。また、生存率や費用対効果、さらには歯科医師からのアドバイスを基に、それぞれの治療法を選ぶ際の判断基準についても解説します。
本記事を参考に、自分にとって最適な治療法を見つける手助けとなれば幸いです。
歯を失った場合の治療法とは?
まずは、30代の一般的な欠損歯数を見てみましょう。さらに歯を失った場合の治療法についても概説します。
30代の喪失歯数
30代においては、喪失歯数は1歯未満です。歯科疾患実態調査では喪失歯数について25〜34歳、35〜44歳という階級が設定されています。厳密には30代の喪失歯数ではありませんが、参考になることに違いはありません。
- 25〜34歳
-
0.4歯
- 35〜44歳
-
0.6歯
欠損補綴治療について
欠損補綴治療とは、失った歯を補うための治療法を指します。これには入れ歯、ブリッジ、インプラントなどの方法が含まれ、広義には矯正治療や経過観察(放置)が含まれます。入れ歯、ブリッジ、インプラントをまとめて欠損補綴物と呼びます。
入れ歯は、天然歯を支えとして着脱可能な装置を作ることで従来のかみ合わせを再現します。ブリッジは前後の歯を土台とし、失った歯を含む被せ物を装着することで、失った歯を補う方法です。インプラントは、歯を失った部分の骨にインプラント体という土台を挿入し、その上に人工の歯(上部構造)を装着することで失った歯を補います。
欠損補綴治療にはそれぞれのメリットやデメリット、特長がありますので、担当医としっかりとディスカッションをして、決定する必要があります。
30代と入れ歯の関係
30代で入れ歯を使用することは少ないものの、必要に応じて部分入れ歯を選択することもあります。本項では30代で歯を失い、欠損補綴治療として入れ歯を選択した場合について考えてみます。
年代別の入れ歯装着割合を知りたい方は下記の記事をご確認ください。
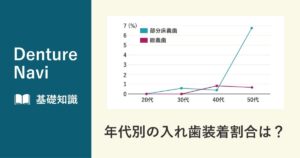
30代の入れ歯使用割合
30代における入れ歯の使用者は少数派であるものの、30代後半では部分義歯を必要とするケースがしばしば見受けられます。欠損歯数が少ないため、統計上は総入れ歯の人はいないとされています。
- 30〜34歳
-
部分入れ歯:0% 総入れ歯:0%
- 35〜39歳
-
部分入れ歯:1.2% 総入れ歯:0%
入れ歯のメリットとデメリット
入れ歯のメリットは、歯を失った際に比較的短期間に補える点です。部分入れ歯は周囲の健康な歯を削る量が少ないことも特長です。一方で、デメリットとしては、入れ歯の違和感や咀嚼能力が落ちる可能性があることなどが挙げられます。また、周囲の歯を削る量は少ないものの、入れ歯を支える歯が負担過重になったり、虫歯になったりして、最終的には周囲の歯を失ってしまうリスクを秘めています。
30代における入れ歯以外の欠損補綴治療の割合
30代では、入れ歯以外にもブリッジやインプラントを選択するケースがあります。これらの治療は、一般的に入れ歯よりも安定感が高く、自然な装着感を提供するため、欠損歯数が少ない年代ではよく利用されます。
30代のブリッジ使用割合
全ての欠損補綴治療のうち、30代でのブリッジ使用している割合を以下に示します。30代前半で欠損補綴物を装着している人の100%(全て)はブリッジを装着しています。
- 30〜34歳
-
6.7%
- 35〜39歳
-
4.8%
30代のインプラント使用割合
令和4年における30代のインプラント装着率を以下に示します。年齢の増加とインプラントの装着割合が一致していませんが、これは統計上の母集団による影響も考えられます。平成28年の歯科疾患実態調査ではインプラント装着割合は、30〜34歳と35〜39歳の両方で0%でしたので、30代のインプラント使用割合は増加傾向にあると考えられます。
- 30〜34歳
-
1.3%
- 35〜39歳
-
0%
筆者の臨床実感としても、35〜39歳におけるインプラント装着割合は0%ではないと考えれます。少数ではありますが、30代後半でインプラント治療を行っている人います。
30代が欠損補綴治療を選ぶ際の基準
30代で欠損補綴治療を選ぶ際には、長期的な視点を持って治療法を選択することが求められます。特に、生存率や費用対効果、そして歯科医師のアドバイスを重視し、それぞれの治療法のメリットとデメリットを比較することが大切です。
生存率
治療法選択の基準のひとつとして、生存率、すなわち治療がどれだけ長持ちするかが挙げられます。一般的には10年後の欠損補綴物の生存率、つまり10年生存率が指標とされます。
10年生存率は、入れ歯で約50%、ブリッジで30〜90%、インプラントで約90%です。
費用対効果
欠損補綴治療を選ぶ際、費用対効果も重要なポイントです。インプラントは初期費用が高額ですが、長期的な視点で見れば、維持管理費用が抑えられることがあります。一方、入れ歯は初期費用は抑えられるものの、生存率の低さがネックです。ブリッジは状況によっては中程度の費用で、高い生存率を得られる点が特長です。
30代という若い年代で選ぶ欠損補綴治療に絶対的な正解はありません。それぞれの口腔内の状況、経済的な状況を踏まえ、歯科医師との密な相談が一番需要となるでしょう。
歯科医師からのアドバイス
治療法の選択において絶対的なものはありません。特に30代では将来のことを考えた治療が重要であり、専門家の意見を取り入れつつ、自身が納得できる治療法を選択することが重要です。
少ない欠損歯数においてはインプラント治療がスタンダードとなりつつあります。その一方でインプラント治療には、高額な治療費と外科手術が伴う点を考慮しなくてはいけません。
信頼できる歯科医師と共に治療計画を立てることが、健康的な口腔環境を維持するカギとなります。
まとめ
30代での歯の喪失は必ずしも珍しいことではなく、適切な欠損補綴治療を選ぶことが健康な口腔環境を維持する鍵となります。義歯は比較的安価で治療期間が短いため、多くの30代の患者に選ばれていますが、使用感や見た目に関するデメリットも考慮が必要です。一方で、ブリッジはコストパフォーマンスに優れた治療ではありますが、隣接する健康な歯への影響が避けられません。インプラントは高い生存率と周囲の歯への悪影響の少なさが魅力的ですが、費用が高額です。
これらの欠損補綴治療を選ぶ際には、費用対効果や自分のライフスタイルを総合的に考え、歯科医師のアドバイスを参考にすることが重要です。各治療法には特有のメリットとデメリットが存在し、個々の状況に最適な選択を見つけることが理想的なのです。



